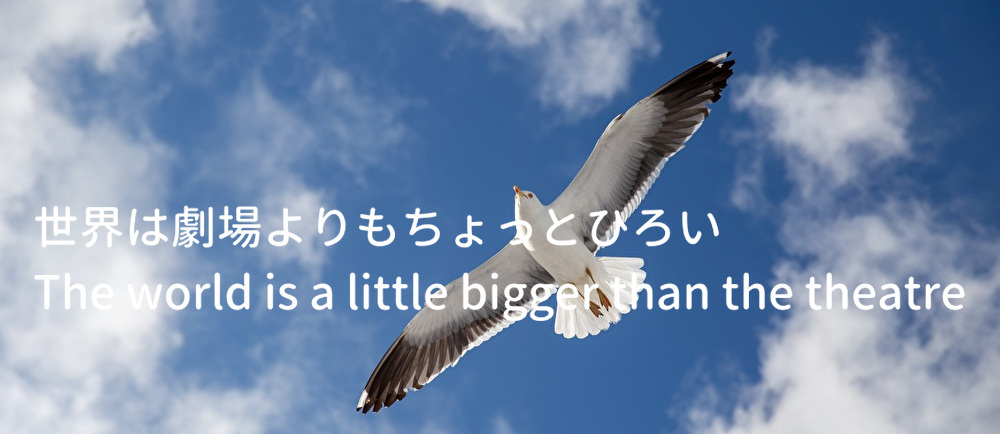
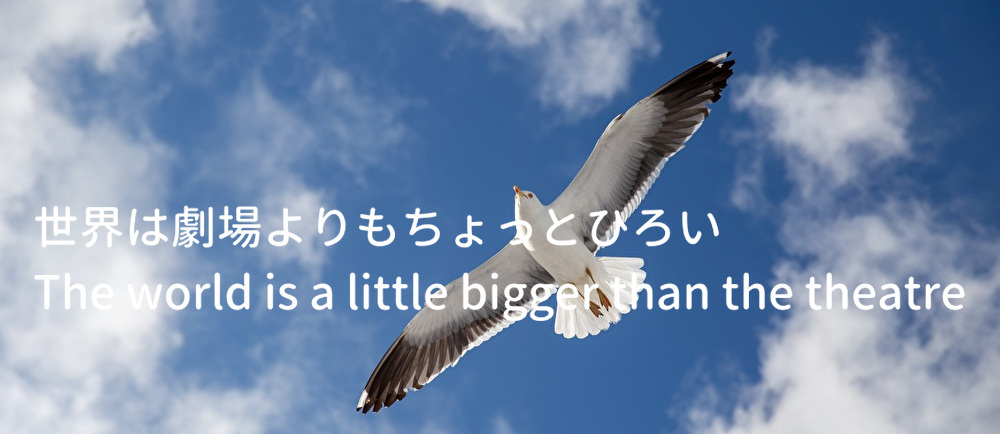
3月31日
生涯に何度も経験しないだろう一カ月が過ぎた。
1日のdiaryに書いた「暴れたいなー」のひと言は遥か。
振り返って見ればいかにもお気楽な戯れ言めいて恥ずかしい。
「劇場」や「芝居」について、ロマンではなくリアルを。
生きていかなければ……って、チエホフかい、糞!
3月30日
延期した劇場創造アカデミー修了上演の再構築。
状況は決して好転したわけではないが、劇場スタッフのバックアップ体制を含めて、周辺環境は少し落ち着いた。
ボンドのテキストは直接、広島、長崎にインスパイアーされたもの。
3.11以前のリハーサルでも、日々、執筆から30年近くの時を経たいまも有効な作者の強靱な構想力を感じていた。
来月半ばからの作業のために、明日から、再び襟を正してテキストに向かいあおう。
3月29日
想像する。
津波が残したヘドロの匂いを。
鉛の床に横たわる疲れ切った影を。
幼子が浴びつづける見えない恐怖を。
終わりなき終わりの果てしのない道程を。
3月28日
夜、劇場で非常勤職員の送別会。
オープン以来、カフェレストランでお世話になった徳永シェフも今期まで。
オープン前の建物で、レストランの照明をあれこれ相談したのがついこの間のよう。
3.11以来の厳しい日々をともにした劇場スタッフの、束の間の慰労会の雰囲気も。
いつもとは違う組み合わせの話の輪がそここに。
3月27日
半休日。
床の間の掛け軸の掛け替え、書斎の整理など。
昼食がてら、久しぶりの町内散歩。
ふっくらとふくらんだ桃の蕾。
自然のいのちの逞しさ。
3月26日
柴田南雄『日本の音を聴く─文庫オリジナル版』(岩波現代文庫)。
古代の石笛、銅鑼、双盤、琴。
その音色への想像力。
知的な好奇心にあふれた簡潔で美しい文章と、ゆったりとしたユーモア。
後半は、シアターピースを通して一緒に過ごさせていただいたかけがえのない時間の断片が、懐かしく次つぎと。
3月25日
節電。
明かりが消えた「暗い町」というと何かマイナーなようだが、感じは決して悪くない。
いままでの「明るすぎる町」がどこか異常だったように思う。
駅エスカレーターの部分使用、電車内の暖房切断なども同じく。
自粛や節約ではなく、ほんらいのヒューマンスケールへの回帰。
3月24日
3.11からの気ぜわしい日々。
「さてと……」と立ち止まったというわけでもないが、ひと息ふた息深呼吸。
劇場のデスクで、今後の活動に向けての整理いろいろ。
日がたつにつれて、コミュニティシアターの真価が問われる場面に次々と遭遇しそうな予感が。
なにはともあれ、劇場スタッフの緊張と疲労の緩和を工夫しないと。
3月23日
基準値はオーバーしているが、とりあえず人体に影響を与えるものではない。
そりゃそーだろう。
しかし、基準値が基準値であることも事実。
おまけにその値自体が二倍とか十倍とか、どんどん勝手に変更されている。
一体、どこで誰が?
訃報
弟、敦(享年64)が亡くなりました。
生前のご交誼に感謝し、謹んでお知らせいたします。
長らく「ストーリー・レーン」代表取締役をつとめ、日中合作オペラ『魔笛』や黒テント+オンシアター自由劇場のアビニョン公演の総合プロデューサーをはじめ、数々の仕事をともにしました。
21日6時より通夜、22日12時より告別式をとりおこないます(喪主、妻、聖子)。
場所、青松寺(東京都港区愛宕2-4-7 03-3431-3087)
(「五柳五行」は23日までお休みします)
3月18日
とりあえずいったん中断、もろもろ延期を決定したアカデミー関係予定の事後策いろいろ。
事後策というよりは代替案の検討か。
あまり先のばしはしない形でのスケジュールと施設の調整をはじめる。
劇場そのものは利用カンパニーの意向を汲みながら、坦々と平常業務を。
二階カフェのいつも通りの落ち着いた雰囲気にこころが安らぐ。
3月17日
「過剰反応」と笑ってもらいたい。
それが願いだ。
劇場創造アカデミー修了上演、延期を決める。
東京以西からの上京組には、とりあえず帰郷を促す。
根拠は……ない(それが怖い)。
3月16日
何人かの俳優たちの立ち姿が一変した。
自由、かつ即興的な演技の中でぐいぐいとテキストの読みを深めていく。
こうなると演出の生半な「読み」など、到底太刀打ちが出来ない。
面白い稽古場。
二年間ともに過ごした研修生たちと、ようやくここまでやって来た。
3月15日
装われた日常の背景で確実に進行しているもうひとつの時間。
3.11以来、日々、「リアル(現実)」なるものの本来の意味を文字通り体験して(させられている)いる。
思考も行動も、常に「リアル」にかかわりつづけること。
見知らぬふり、忘れたふりでやり過ごすことは不可能なのだから。
なによりもまず、おのれ自身の「リアル」を見つめ直さなければ。
3月14日
終了上演の稽古、最終コーナーへ。
全体に一段ステージをあげた感じで、もうひとつ面白い稽古場になりそうだ。
騒然とした周囲について思いはいろいろあるが(ことに、地震直後の政府発表から懸念していた福島原発について)、こういう時のネット環境での発言は慎重に。
ブログや「つぶやき」に氾濫するさまざまな情緒的言説を片目に自戒。
「持ち場持ち場」での役割の見極めが肝腎かと。
3月13日
首相から国民へのTVメッセージ。
電力維持のための輪番停電を告げながら、二、三度涙目。
ったく、こういう時には偉い人ほど「平常心」を願いたい。
ついでに、与野党そろって板につかない作業着姿というのもなんだかなー。
民社党党首福島女史まで、胸に党名を張り付けたカーキ服ね。
3月12日
仙台には十年前までは家の墓があった。
青森、山形、岩手、宮城、福島と、黒テントの旅公演でお世話になり、その後も親交をつづけている知人が多い。
あの人、この人の顔を思い浮かべて、ひたすら無事を祈る。
稽古の合間、地下三階から二階事務所に階段で戻り(本日、劇場のエレベーター全日休止)、原発関連の情報をTVで。
緊急時の的確な情報伝達の難しさ。
3月11日
終了上演の稽古開始直後、船底のような揺れ。
いままで経験したことのない揺れの感じと継続時間。
建築後二年の建物、地下三階ということで不安感はなかったが、出来事の重大さを直感する。
予想しいた通り、携帯電話、まったく役に立たず。
夜、TVで繰り返し放映されている福島原発関連の政府発表が、とても心配。
3月10日
来日中のダニー・ユンとともに、昨日は交流基金、今日は早稲田大学演劇博物館と、三年計画の能・崑劇交流計画関連の打合せがつづく。
終わって、ダニーを博物館に案内。
開催中の梅山いつき企画、「広場をつくる」展を見る。
坪内逍遥自筆の劇場系統図、初見。
そうか、坪内さんもこんなこと考えてたんだ、と、興味津々。
3月9日
アカデミーⅡ期生の「劇場環境論」。
担当の中村洋一(社会学/立教大学)さんの今期最終授業に招かれて、対話形式で二時間。
中村さんの柔軟な思考とゆったりと暖かな人柄には、毎回、とても励まされる。
今日の話題は、現代社会の速度感、コミュニティの規模と実質についてなど。
発生以来、終始、文字通りのヒューマンスケールを保ちつづけてきた「劇場」「演劇」再考へのヒント多々。
3月8日
朝、劇場への下車駅、高円寺のプラットホームで奇怪なポスターを発見。
「駅員、車掌につばを吐くのは犯罪です」というコピーと、電車の車掌の顔めがけてつばを吐きかけている若い男のカラーイラスト。
どういうことだろ、これは?
例外的な非常識人にたいするJRの過剰反応か、それともつば吐きの日常化か。
いずれにしても、いまの日本、病気だな、確実に。
3月7日
わが胎内の現状を調べるために、半年ぶりのCT検診。
造影剤とX線照射についての事前説明、同意書の提出など、事情はわかっていてもやはりちょっと緊張する。
検査器に横たわり、二十分ほどの事前検査(だと思う)いろいろ。
そのあと、呼吸をとめる練習。
「息を吸って下さい」「止めて下さい」……(一分半経過)……おいおい。
3月6日
「社会科」という言葉をときどき使う。
二十年ほど前までは、企業が新人研修というかたちで徹底的に企業流「社会科」をたたき込んだ。
さて、定年退職後の彼らに、その「社会科」はどの程度使い物になっているのか。
いま、若者たちは企業流「社会科」習得の機会さえ奪われ、あてどなく漂流する。
あらゆる挨拶語を「お疲れさまです」の一語で間に合わせながら。
3月5日
今年は春までの日々がなんだか思わせぶりに行ったり来たり。
昨日の朝は外のバケツにうっすら氷が張っていたのに、今日はPコートではなく薄手のトレンチコートでも、新宿の町を歩きながら少し汗ばんだ。
三越から丸井に主が変わった三丁目交差点界隈は、すっかり二十代目当ての町に化粧替え。
高校時代の遊び場のひとつということもあって、自分が町の雰囲気を素直に呼吸する若やいだ気分になるのが面白い。
だけど、お目当ては昔ながらの「追分団子」。
3月4日
上演まで残り三週間、研修生たちの集中力がようやくひとつの方向にまとまり出す。
どんな仕事でもそうだが、劇場でも、この集中の感覚を平常心として身につけるのがいちばん難しい。
「眼高手低」は若者の常だが、近頃はその「眼高」の内実までもがなべてお粗末。
他人まかせの理屈はいい。
自分たちの感性を発揮できる集中力のありかを知れ(ありゃりゃ、これではまるでダメだしノート。矛先をそのまま我が身に向けなおさないと)。
3月3日
稽古の日々は、演出する者にとっては、かならずしも作品づくりとの関係に限定せずにひたすらテキストの読みを重ねていく毎日でもある。
少なくともぼくの場合はそうだ。
いま、この時にエドワード・ボンド『戦戯』(私訳)を選んだというか、出会ったのは本当に僥倖だったと思う。
四十年前のこの作品からの根源的な問いかけは、驚くほど古びていない。
その普遍性が、困難ではあるけれども、未来へのたしかな希望を紡ぎだし、元気づけてくれる。
3月2日
一緒に芝居づくりをしていると、アカデミー研修生との関係が日々変化していくのがわかる。
ひとりひとりの個性とともに、この二年間、アカデミー側が何を伝えられたか伝えられなかったが、次第に明瞭になる。
伝えられなかったこと……それを限界ではなく、可能性と捉え返す腕力。
芝居はひとりでは出来ない。
おそらくいま、もっとも要求され、同時に力づけられているのは新米演出家イクタ トサトウ。
3月1日
劇場創造アカデミー修了上演稽古冒頭、イクタが持ち込んだ伊藤貫の「世界秩序再編論」めぐって話し合い。
ネット動画をはじめとして、最近、あちこちで見かけるアメリカの経済アナリスト出身の評論家。
サトウの感想は、「核武装すべし」の結論へいたる歯切れのいい大風呂敷、そのわかりやすい語り口こそが胡散臭い。
研修生の反応は……ま、素直な小鳥。
暴れたいなあ。
