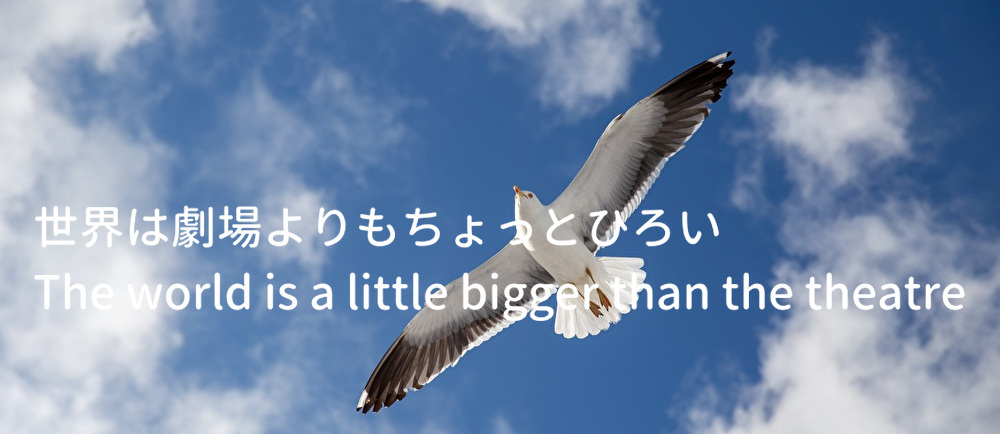
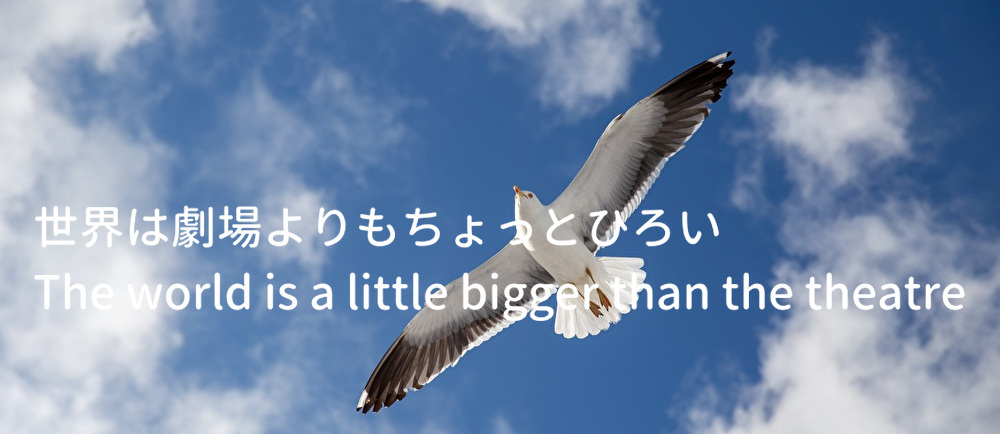
9月30日
ワークショップ、最終日。
五日間のまとめとして、観客一人(昆劇院院長)の前で三十分ほどのピースを上演。
昆劇院から参加の若い二人、孫晶、唐沈について、院長からは厳しい言葉があったが、まっすぐに演技に向き合う態度と、行われていることへの的確な把握という意味で、ふたりとも、実に気持ちよく、また力のある協働者だった。
彼らの演劇へのひたむきさをしっかり受け止める作業。
次の作業(上演テキストづくり)のハードルは高い。
9月29日
昨日深夜到着した野田昭彦さん(国際交流基金)とともに、午前中、昆劇院院長とミーティング。
「能、昆劇交流」三年計画の内容確認が主な目的だったが、最後に院長から思いがけない新提案があった。
とりあえず帰国後の検討を約して預かる。
ワークショップ四日目。
俳優たちの積極的なかかわり合いによる即興のふくらみが、何カ所かの「演劇」を確実に現出する。
9月28日
昨日までの即興をもとに、今日から三日間、今回のワークショップの成果としての小ピースづくり。
ジャンルの異なる(昆劇、京劇、現代演劇)の出演者たちのコンビネーションに、少しずつ方向性が見えはじめた。
30分程度を予定しているピースの、約半分までをスケッチ。
二回目の繰り返しで、今回『霊戯』の基本様式についての方向性が見える。
夜、孫晶の案内で、いま南京の若者に大人気という四川料理のチェーンレストランで食事会。
9月27日
身体感覚。
かすかな違和感の記憶。
自分にとっての演劇のすべては、おそらくそこにある。
ごく初期から現在まで、この観点からの読み解きをおこなえば自作のテキスト分析はおそらく造作もない。
南京の町を歩きながら、そんなことをふいに確信する。
9月26日
昆劇の劇場で、『霊戯』ワークショップ一日目。
最後の一時間をつかって、郭宝崑『霊戯』元テキストの読み合わせ。
日中両国語が混在する俳優たちの声を聞くうち、突然、こみあげてくるものがあった。
ほかでもない南京の地で、日中両国の俳優によって読み起こされる霊魂たちの言葉。
宝崑のたくらみを引き継ぐために、この思いを単なる感傷に終わらせないエナジーの持続を。
9月25日
南京へ。
成田を離陸する機内の窓から下を眺めながら考える。
飛行機がある高度にまで上昇すると、眼下の風景から人の気配が消える。
時間についても、もしかしたら同じように言えるのではないか。
俯瞰された歴史的時間に、等身大の人間の営みははたして存在しているのか。
9月24日
明日からの南京行きに備えて、一日、休養日。
TVで放映された「家族、側近が語る周恩来」を有線チューナのHDに録画しながら、ところどころ休息を入れて見る。
全四時間。
「不倒翁」の矜持と葛藤。
政治家というよりは、あたかも国家に生涯を捧げた現代の科挙。
9月23日
秋の彼岸。
水道橋宝生能楽堂で「響の会」。
『当麻』鈴木寛二、『俊寛』西村高夫。
狂言は山元東次郎『八句連歌』。
終わって、笛田宇一郎さんと久しぶりにお茶。
9月22日
鰯雲の美しい台風一過の朝の空と思っていたら、夕方から小雨、肌寒い。
南京でおこなう『霊戯』工作坊準備。
昆劇院の若手俳優+京劇の張さん+笛田宇一郎さん。
未知の出会いへの期待と緊張感。
あくまでも自然に、かつ大胆に。
9月21日
道楽者と職人とは両立するだろうか。
きっかけは道楽。
手筈は職人。
当たり前の話だがアートとは無縁。
人を巻き込み、巻き込まれながら……罰のあたらぬよう、神妙に。
9月20日
山元清多を忍ぶ会。
会場の赤坂TBSの建物にはじめて入る。
二十代、三十代、TBSラジオは大事な仕事場のひとつだった。
時の流れを考えれば様変わりは当たり前だが、うーん、それにしても。
元さんが呼び寄せた懐かしい顔、顔。
9月19日
終日、自宅作業。
メモに従い、事務仕事いろいろ。
合間にシーズンが始まったNFLの第一週ハイライトをTVで見る。
試合前、中、後の各チームのベンチ、ロッカー・ルーム風景に注目。
コーチそれぞれのサービス精神と演技力……他人事ではなく。
9月18日
日差し強く気温も高いが、間違いなく秋の空。
世田谷の病院に母を見舞い、その足で芝へ墓参り。
締めは、池袋演芸場(夜席主任、柳亭市馬)。
乗り継ぎの電車で八代目林屋正蔵『正蔵一代』(青蛙房/初版 昭和49年 新装版 平成23年)を読む。
血のめぐりの爽やかな一日。
9月17日
『ふたごの星』、千穐楽。
ようやく歯車を一齣だけ回せたたような気がする。
座・高円寺のレパートリーづくりに本格的にかかわれたこと。
アカデミーの修了生二人が、学んだ劇場でデビューできたこと。
その作品が子どもとともにある舞台だったこと。
9月16日
9月26日から始まる三年目の『旅とあいつとお姫さま』。
今日と明日の二日間、稽古場に参加。
日本語のセリフを中心に細部のチェック。
完成度の高い作品だけに、慎重に。
終わって、演出のテレーサから『ふたごの星』について丁寧な感想をもらう。
9月15日
日々の営みを俯瞰的に眺めれば、間違いなくコメディであるだろう。
思い込みや思い違い、思惑外れ、挙げ句の果てのインチキ臭い辻褄合わせ、などなど。
冷や汗、脂汗は日常茶飯事、日に何回は足をすべらせ、スッテンコロリとものの見事にひっくり返っている。
バナナの皮はいたるところに。
せめて、チャップリンのペーソスではなく、キートンの不屈なポーカーフェイスで。
9月14日
日暮里。
11月に『霊戯』を上演するd-倉庫を下見に。
駅から劇場までの布屋街をゆっくり散策。
リボン、テープなどの小物、皮屋など楽しい店先が次々と。
劇場前のデッキで、夕焼け空を眺めながら待ち合わせのスタッフを待つ。
9月13日
終日、劇場の自室で過ごす。
これからの仕事の整理、および『霊戯』の準備いろいろ。
合間に個人劇団「鴎座」のひとり総会。
もっと緻密に、もっと大胆に。
夜、『ふたごの星』一般公演、観劇。
9月12日
黒テント総会に久しぶりに出席。
発言を控え、議論を傍聴。
創立以来四十年余、同じような議論を何回繰り返してきただろうか。
完全に納得しているわけではないが、後悔やあきらめはない。
終わって、出席劇団員全員で、元さん、山元清多の一周忌を忍ぶ。
9月11日
9.11十周年、3.11から半年。
11月に上演する、「鴎座」第Ⅱ期上演活動3郭宝崑『霊戯』宣伝素材の原稿を書きながら、「演劇、何故?」をしきりに思う。
おのれを語らなければならない。
おのれに語りかけなければならない。
応答の是非にまどわされることなく。
9月10日
『ふたごの星』、一般公演日(マチネ)。
終わって、近所の居酒屋で中日懇親会。
舞台監督の津田さんはじめ、スタッフ、キャストが集いなごやかにワイワイ。
パートナーの銀粉蝶さんと観劇に来てくれた生田萬さん、途中から合流。
生田さんとは、アカデミーの修了上演、Ⅳ期生のカリキュラムなど、打合せを少し。
9月9日
三カ月に一度の定期検診日。
今回は血液検査と心臓エコーを追加。
いつもの通り、問診一分、「順調ですね」のひと言+薬の処方箋。
帰り道、薬局から受け取ったばかりの大量の薬を電車に置き忘れ。
このまま行方不明だと、ちょっと大変なことに(二度目は薬代に保険がきかない!)。
9月8日
アカデミーⅡ期生の後期授業はじまる。
名目は「演技ゼミ」だが、修了公演、および修了後の進路についての長期オーディションの意味合いも。
研修生ひとりひとりとしっかりと向き合い、聞き取るべきことを聞き取り、伝えるべきことを伝えていきたい。
夕方、今年修了のⅠ期生三人(古賀、下村、砂川)のパフォーマンス・オーディション。
可能性に希望をもって、さらに着実な活動をつづけて欲しい。
9月7日
世田谷の病院に母を見舞う。
車椅子を押して院内と玄関前の植え込み脇を散歩。
夕方の空は秋の気配。
院内の喫茶店で珈琲。
絶食中の母は香りを楽しむ。
9月6日
午後の小学四年生招待公演のあと、夜、『ふたごの星』一般公演。
小さな子どもたちの姿もよりも、大人が多い観客席の応答を最後部の席から確認。
「くすっ」と笑ったり、舞台上の人物の目の動きを追って素早く視線をうつしたり、生き生きとした小さな反応と息づかいがうれしい。
日々の生活の中に、ぽっかりとひらいた隙間の時間はつくれたのかな、と、ちょっと安心する。
さて、『霊戯』は……
9月5日
終日劇場で、事務仕事いろいろ。
さて、頭を切り換えて、二年ぶりの「鴎座」上演準備へ。
レパートリーは、十年来の懸案、郭宝崑の遺作『スピリッツ・プレイ』。
来年は、没後十年を記念するシンガポールでの上演も控えている。
先入観をすべて捨てて、真っ正面からテキストに向かおう。
9月4日
休日。
入院中の母を、啓子と見舞う。
夕食は、吉祥寺のサトウで松阪肉のステーキを奮発。
帰宅後、イランのジャリリ監督の初期作品『ダンス・オブ・ダスト』(1998年製作)をDVDで見る。
瓶、缶、プラスチック製品のゴミ出し。
9月3日
水木しげる『ねぼけ人生』(ちくま文庫/原書は1982年刊)。
うーん、凄い!
なんだ、この人は?
よーするに、生きている人。
遊んでいる人(たとえば、わたし)はただただため息。
9月2日
『ふたごの星』、初日。
心配された天気もなんとか一日もち、劇場のロビーは朝から元気な子どもたちの声があふれた。
B2フロアのgalleryアソビバでは、明日からはじまる「舞台美術家島次郎展」(展示充実、必見!)の飾りつけ。
座・高円寺2では南相馬の市長を迎えて、区主催の防災シンポジウム、阿波おどりホールでは座・高円寺の運営評価委員会と、劇場スケジュール満載の一日。
というわけで、『ふたごの星』初日乾杯はとりあえず楽屋ロビーであっさりと。
9月1日
『ふたごの星』、舞台稽古、無事終了。
初日の明日、開演は午前10時30分。
開館三年目。
『ピン・ポン』に引きつづいての、子どもたちへの舞台づくり。
客席からの応答を待つ。
