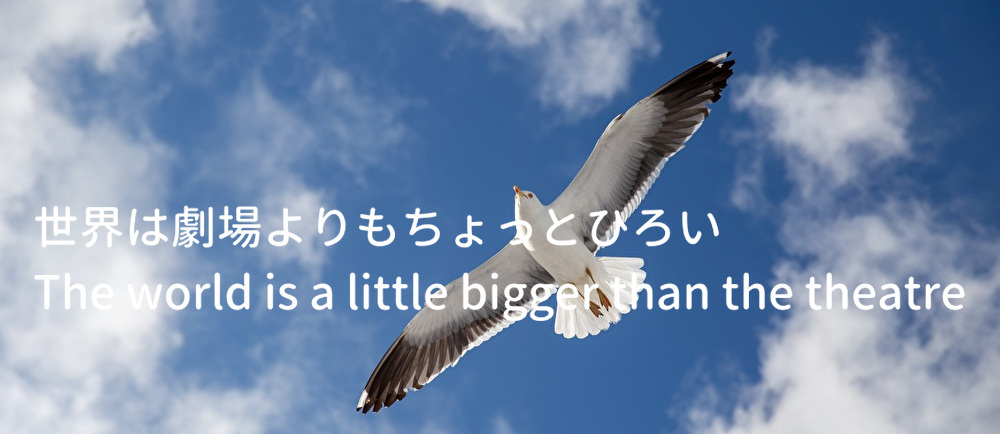
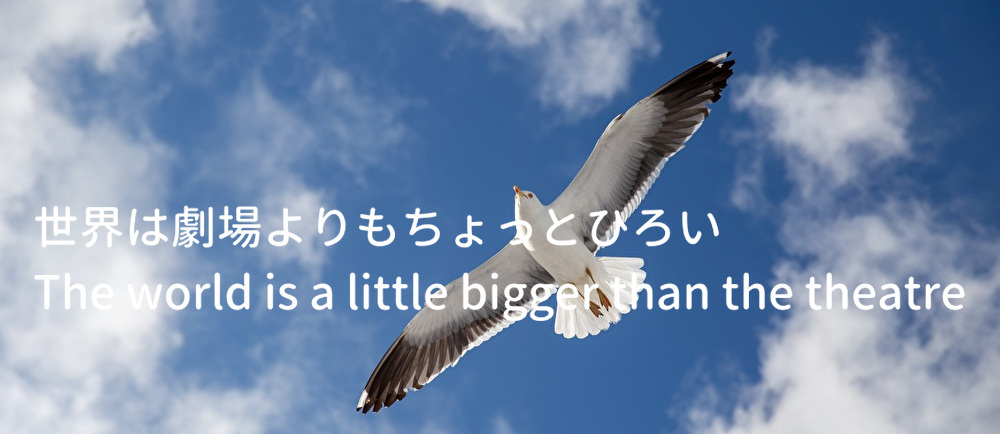
8月31日
昨日に引き続き、午前中から明かり合わせと場当たり。
ようやく、稽古場での作業が劇場とリンクしてまとまり始める。
劇場入りしてから四日間という日程の余裕は、決して充分とはいえないが、それでもありがたい。
作業が順調にすすみ、四時から予定外の通し稽古を二回。
終わって、音楽のKONTAさん、映像の川上くん、最後の詰め作業。
8月30日
『ふたごの星』、明かり合わせと場当たり。
いつでもそうだが、これまで稽古場で積み上げてきたいろいろを、あらためて劇場空間になじませていく作業は思いの外手間がかかる。
俳優の演技はもちろん、頭の中で勝手に出来上がっていた芝居の「空気感」が、あたらしい空間に投げ出されて戸惑っている。
過度な「計算」は得意ではないし、好きでもない。
なるようになる、というほど無責任ではないが、この期におよんでも、なるようにならせる「即興性」の面白さは大切にしたい。
8月29日
『ふたごの星』、劇場仕込み日。
大道具、照明、音響、映像と、スケジュール通り、順調な作業進行。
終わって、楽屋で照明の斎藤茂男さんの誕生日を祝って乾杯。
二十年間以上、ほとんどすべての舞台づくりをともにした、大切な劇場仲間。
たくさん無理も言ったが、舞台照明についての実験を積極的に受け入れてくれた同志。
8月28日
『ふたごの星』、稽古場最終日。
ダブルキャスト両組の通し稽古を一回ずつ。
映像ラフも出来上がり、明日からの劇場入りに備える。
五年間探ってきた子どもとともにある演劇。
これまでとは全く違った稽古場がようやくかたちになった。
8月27日
東京高円寺阿波おどり開会式出席のあと、劇場に戻り『ふたごの星』稽古。
懸案の場面を確認したあと、通し稽古を二回。
ゼペットの福田さんに発注していた小道具が全部揃う。
青い星、光るヒトデ、海蛇、海蛇王の髭など、それぞれにちょっとした工夫が凝らされていて、楽しい仕上がり。
俳優たちには、最後の最後まで、ちょっとした工夫よりも大胆なscrap & buildを期待。
8月26日
菅直人民主党代表の辞任表明。
「政局」と呼ばれるこの国の権力抗争の不可解さ。
というか、理念の希薄さ。
それとも、誰かが、どこかで、何かを仕掛けているのだろうか?
我こそが、とのたまいそうな面々は数多く思い浮かぶが。
8月25日
『ふたごの星』、通し稽古一回と細部の確認。
見えているものは出来るだけシンプルに明るく、支えているものはより深く、複雑な色合いで。
宮澤賢治のハードルは高い。
賢治自身はもちろんだが、いま何故賢治なのか、という問いへの解答が。
答は「詩」だと見当はつけているが。
8月24日
iPhone読書。
漱石『それから』読了。
めったにないことだが、この歳になって、珍しく主人公の代助に感情移入。
主筋の人妻への恋愛感情はおくとして、作中の立ち居振る舞い、おりおりの感情の起伏など、いちいち納得。
要するに「高等遊民」(死語)の心情か……おそらくね(苦笑)。
8月23日
稽古修了後、アカデミー修了生の川上くん担当の映像素材を確認。
スクリーンに投影された映像が、打合せとは微妙に違っていて「あれ?」っと思ううちに、カラフルな「誕生日おめでとう」コメントに変わる。
あとは、稽古場にいたキャスト、スタッフはじめ、劇場スタッフ、アカデミー生も加わり、久しく経験したことのないお定まりの展開。
暗闇の中、入場したケーキの上に立ち並ぶ蝋燭をなんとかひと息で吹き消す。
プレゼントは、風呂場用小プラネタリウムもどき(!)。
8月22日
「劇場へいこう!」企画、事前懇談会。
区内の小学校長、担任の先生、区の担当者の他、横浜をはじめ近隣の「おやこ劇場」関係者など、十数名が参加。
座・高円寺のこども事業全体の概要、「劇場へいこう!」の趣旨、および『ふたごの星』取り組みを説明、意見交換をおこなう。
終わって、参加者全員が『ふたごの星』の通し稽古見学会。
俳優たちが思いのほかのびのびと、楽しそうに演じていたのが印象的。
8月21日
『ふたごの星』、通し稽古三回。
細部の仕上げに向かわずに、全体の大きな流れの把握についての再検討をこころがける。
俳優が舞台に立つということへの「寛容」さ。
翻って、俳優を選択するときの「厳密」さ。
俳優は劇場の「主」か、はたまた「従僕」か?
8月20日
『ふたごの星』稽古場、ようやく作品全体の構成がまとまる。
これから約十日間、通し稽古を繰り返しながら、内容をさらに深めていきたい。
八十年代初頭、黒テントで上演した『西遊記』で発想を得た、「物語る演劇」について、あたらしい一歩を踏めそうな感触。
「一層の 無邪気さと ユーモアとを 有さざれば 全然不適」。
↑「ふたごの星」草稿に付されている賢治自身の覚書。
8月19日
見えないものを見る。
まったくの「無」ではない。
たとえば星座。
思わず見とれるほどの輝きを手がかりに星々を名づけ物語をつむぐ。
星のない夜空の下、子どもたちとともにつむぐ物語とは?
8月18日
稽古前、自宅近くの小学校で、区立小学校長会役員の先生方と打合せ。
今年の「明日の劇場」事業の趣旨説明と協力のお願い。
区内の小学校四年生全員を劇場に招待するこの企画は、何といっても、座・高円寺自主事業の大きな柱だ。
事業内容に現場の声を反映するための、今後とも、風通しのいい関係づくりを地道につみ重ねていきたい。
参加された先生方からの率直な提言や嬉しい感想など、実りあるひとときとなった。
8月17日
『ふたごの星』稽古再開。
前半部分の流れがようやく形になってきた。
明日からは、「通し稽古」を目指して、後半部分を集中的に。
今回、現場スタッフはアカデミー修了生を含めて初々しい若手が中心。
技術的なことはともかく、まず、芝居づくりの楽しさと稽古への参加方法をしっかりと伝えたい。
8月16日
休暇最終日。
帰宅途中、横浜元町に寄り道。
肩掛け鞄を衝動買い(たしか、去年も!)。
帰宅後、TVでドニゼッティ『ルクレツィア・ボルジア』(バイエルン州立歌劇場)を見る。
タイトルロール、グルベローヴァの歌唱とともに、クリストフ・ロイ(初見)の演出に拍手。
8月15日
斎藤憐さんの戯曲によれば、「天皇陛下が戦争は終わった」と言った日。
東京湾に停泊したアメリカ軍艦ミズリー号上でおこなわれた、降伏文書調印式は半月後の1945年9月2日。
日本側は天皇、政府の名のもとに重光葵外務大臣、大本営の名のもとに梅津美治郎参謀総長が署名した。
連合国側は連合国最高司令官ダグラス・マッカーサー以下、アメリカ合衆国、中華民国、イギリス、ソビエト連邦、オーストラリア、カナダ、フランス、ニュージーランド代表が署名。
隣国韓国韓国では、8月15日は解放、独立を祝う「光復節(カンボッチョル)」。
8月14日
電車で下田に出て、14、15日の二日間おこなわれる下田八幡神社例大祭(下田太鼓祭り)初日を見物。
神輿渡し、各町内が繰り出す太鼓山車とお囃子、太鼓橋など、見どころの多い祭り。
これまでも、何度か通りがかりに出会っていたが、今回は、半日かけて祭りそのものをじっくりと見る。
三河から伝わり、明治末期頃から、浅草三社祭りの影響を受けて現在の形になったという。
さまざまな世代の町衆にそれぞれの見せ場が用意されている自分たちの町のための祭りを、啓子とふたりで相伴。
8月13日
安藤鶴夫『文楽 芸と人』(朝日新書)、1980年発行、初読。
どちらかというと苦手な著者だったが、面白く読む。
これまで疎遠だった文楽への興味……というか、間歇的に沸き起こる「大阪」文化への関心。
黒テントへの「はじめの一歩」に手を差しのべてくれた1970年代の大阪。
思い出す顔いろいろ。
8月12日
「つくる」のではなく、「出来上がる」。
もちろん、そのためには考えもするし、行為もする。
しかし、最後は「ゆだねる」。
他者とともに、お互いに「ゆだね」合う。
息を殺し、「出来上がり」の行方を見つめながら。
8月11日
人はみんなふたごなんだよ、もうひとりの自分を探して旅をしているんだ……
今回の台本からまず最初に削った、世田谷パブリックシアター版『ふたごの星』のせりふ。
どこかで気楽に構えていると、ついこんな、ただの説明のようなせりふを書いてしまう。
演出プランにしても同じことだ。
俳優と観客(今回は、大半が学校という枠組みを通して、半ば強制的に客席に座らされる子どもたちだ)たちに、誠実に、無心に向かう難しさ。
8月10日
この休暇は、つまるところ『ふたごの星』漬けの日々。
仕上げを目前に稽古を中断して、これまでの作業を振り返り、構想を再吟味する。
なによりも、もう一度、賢治の原作にもどり、読み直しを徹底的に。
方法としての善し悪しはおくとして、機会は機会だ。
存分に利用しよう。
8月9日
稽古を中断しての長期休暇ははじめての経験。
例年の通りの山籠もりだが、息抜きになるかどうか。
何はともあれ体のメンテナンスを。
ここ数カ月、こころの緊張状態がどこか解けないでいる。
精神→体というよりは、精神←体と思うので。
8月8日
夏休み前の最後の稽古。
終わって、ここまでの進行を整理しながらスタッフ会議。
福岡の展覧会から戻ったtupera tuperaの亀山、中川夫妻も参加(愛娘トコちゃんも)。
舞台監督の津田さんとは初めての仕事だが、ゆったりと安心感をもってゆだねられる感じがいい(ゆだねられた方ははたして?)。
照明・斎藤、音響・島の常連スタッフは、いつもの通り、慌てず騒がす。
8月7日
目下稽古中の『ふたごの星』には、今年三月に劇場創造アカデミーを修了した女優ふたりが出演している。
その他、演出助手、舞台監督助手、学芸担当として一人ずつ。
七月の沖縄市キジムナー・フェスタ関連企画にも、俳優三人がそれぞれオーディションを経て出演、好評を得た。
まだまだ先は見えないが、劇場と結びついた実際的な人材育成について多少とも手がかりの感触はある。
五年後、いや、思い切って三年後を目指して……根気よく。
8月6日
『ふたごの星』、稽古。
二日間の迂回は無駄ではなかった。
更夜、書斎でほっとひと息。
苦労をともにした俳優、スタッフたちも、同じように感じてくれているといいのだが。
とは言え、これでひと安心というわけではない……だよね。
8月5日
小学生以来、はじめて経験する「夏休み」感のない八月。
諸事多忙というような具体的な理由ではなく、なんだろう、「夏休み」特有の能天気な解放感は、もう二度と味わえないような気がする。
代わりに、常時、頭の隅っこにあるなんとも名づけがたい鬱陶しい靄の気配。
3.11以来のそれは、たしかに震災被害や原発事故に由来しているのだが、同時に、それだけにとどまるものでもない。
なだらかな斜面を、次第に加速度を増しながらずり落ちていくような不快とも、不安とも。
8月4日
『ふたごの星』稽古場、当初の進行計画を修正。
ペースを落として、休み前に基礎部分について俳優たちとともにもう少し検討を深ておきたい。
八十年代から黒テントでつみ重ねてきた「物語る演劇」の経験を、そろそろ手放す時のような気がする。
慎重、かつ大胆に未知の領域へ。
子どもたちと一緒に。
8月3日
今日から四日間、座・高円寺、ファシリテーターワークショップ。
今年五月に研修を終えたアカデミー一期生と研修中の二期生、三期生を中心に十五名が参加。
ワークショップのファシリテートは久しぶりだったが、収穫いろいろ。
「集団作業」「コミュニケーション」など、ワークショップにかかわるキーワードの意味をあらためて問い直す。
『ふたごの星』稽古場もまた。
8月2日
まず作品ができる。
それからはじめて、その理論を考え出す。
退屈しのぎの独りよがりの仕儀にすぎず、おそらくは役に立たない上に、あやまった結論に導きかねない。
↑ ジョセフ・コンラッド。
アントニオ・タブッキ『他人まかせの自伝─あとづけの詩学』(岩波書店)からの孫引き。
8月1日
午前中、秋葉原(三井総合病院で処方箋の受け取り)。
劇場へ戻り、カフェレストラン「アンリ・ファーブル」でランチ。
本日の打合せ、銕仙会の清水寛二さん(能、昆劇交流プロジェクト)、舞台監督の津田光正さん(『ふたごの星』大道具)、ゼペットの福田秋生さん(『ふたごの星』小道具)など。
五時から、『ふたごの星』稽古。
前半部分を通しながら、今回上演の表現ポイントを探る。
