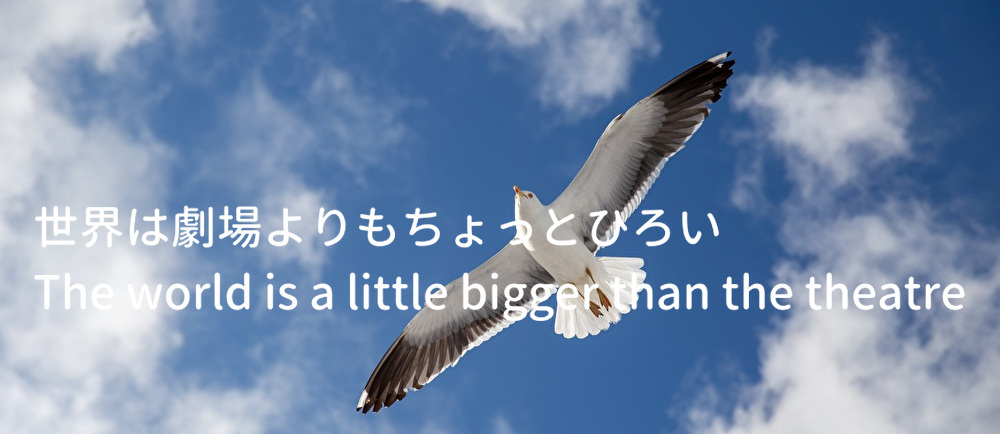
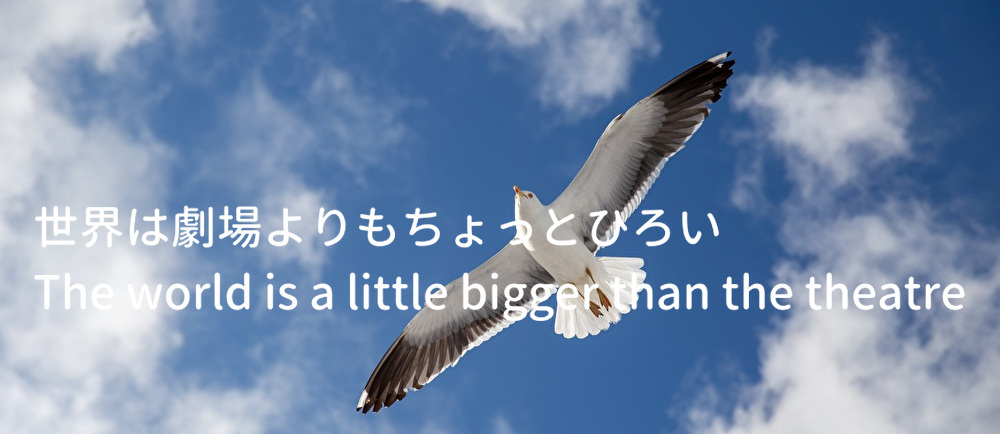
8月31日
今日で八月もおしまい。
一昨日の爽やかさが嘘のような熱暑の一日。
『ふたごの星』舞台稽古の合間、近所の商店街でぶらりと入った古書店の棚が「!」。
しかるべき何某の蔵書をそのまま引き取ったかのような個性の一貫性に興味津々。
手ぶらでは出られず、とりあえずのマーキングに特大版の「大修館漢和辞典」(500円)。
8月30日
『ふたごの星』、劇場での通し稽古二日目。
Wキャスト両組をそれぞれ一回ずつ。
綿密なチームプレイ(アンサンブル)を一時間。
集中力と遊びごころの両立。
俳優にゆだね、俳優の体からの発信を見つめる。
8月29日
今日から四日間、劇場の舞台で、照明、音響、映像を入れた稽古を繰り返す。
劇場レパートリーとして三年目を迎えた『ふたごの星』の、なんとも贅沢な芝居づくり。
俳優に寄り添う照明、音響スタッフもすべて座付き。
上演とは、つくった舞台を見せるのではなく、日々、あたらしく舞台つくること。
恵まれた環境の中で、理想は現実的な確信となる。
8月28日
気温は高いが、風と陽ざしが爽やかな午前中。
久しぶりに、最寄り駅(西荻窪)までぶらぶら歩き。
ふだんはアシスト付き自転車で直行か、バスを使って荻窪経由高円寺のルート。
劇場では、昨日にひきつづいて、『ふたごの星』、場当たり。
照明、音響、映像との連携など、微調整いろいろ。
8月27日
『ふたごの星』、今日から劇場稽古。
明かり合わせと場当たり。
照明plannerの斎藤茂男さんがあたらしくつくった、いくつかの美しい場面に息をのむ。
映像の飯名尚人さんもそうだが、qualityが高く、直感力にすぐれたstaffとの協働はほんとうに楽しい。
こちらの業務は、けいこ場の芝居を劇場にうつすための細々とした算段を根気よく。
8月26日
福島原発関連の本はどれも読書速度が極端に遅くなる。
いま読んでいる船橋洋一『カウントダウン・メルトダウン』(文藝春秋)もそう。
分厚い本をすでに三日間持ち歩くも、いまだ上巻読了せず。
理由はいろいろあるが、何よりもウソ(無作為を含めて)とホントとの見極めが難しい。
大いなるウソの発現を求めて、小さなホントを丹念に探し求める。
8月25日
『ふたごの星』、けいこ場での最終稽古。
昨日にひきつづいて通し稽古を二回。
舞台のすべてを出演者にゆだねられる確信を得る。
同時に、彼らの足を引っ張らない舞台環境の整理。
ある意味、ほんとうの演出作業が明日からはじまる。
8月24日
『ふたごの星』稽古後、東京高円寺阿波おどり開会式へ。
参加の踊り手10,000人、来場者1,000,000人のビッグイベント。
心配された雨雲の悪さもなく、無事開幕(三時間のプログラムの後半、一度、かなりの降りに見舞われたが)。
この祭りを支える町のエネルギーは、間違いなく、「阿波おどりホール」のある劇場、座・高円寺を支える背骨にもなっている。
顔をみかけた町場の方々からの挨拶の声がけがうれしい。
8月23日
70回目の誕生日。
FBの画面で、劇場で、大勢からの祝福を受ける。
とまどいながらも、 素直にありがたい。
どんなにわずかでもいい。
自分の存在が他者と触れ合えている喜び。
8月22日
福島第一原発漏水、事故レベル「3」に。
2011年3月11日以来、過酷事故は現在進行中なのだ。
それなのに、誰が、どのような体制でこの未曾有な事態に対処しているのか、一切それが伝わってこない。
東電?
まさか!
8月21日
『ふたごの星』稽古。
目論んでいる「即興性」をキーワードにした演劇手法をどこまで徹底できるか。
一昨日からけいこ場に同伴して、映像づくりを同時進行中の飯名尚人さんの存在は大きい。
自由な発想によって生まれ、どんどん芝居に参加してくる映像の面白さもそうだが、 なんと言ってもその息づかい。
「もっともっと」という無言の励ましとプレッシャー。
8月20日
「鴎座」Ⅱ-4、予約申し込み受け付け開始。
管理に使っているシバイエンジンのリストページには、午前中、早くも「通し券」二枚の申し込みが。
これから二カ月間、文字通りの手づくり上演活動へ幸先のいいスタート。
世阿弥『金島書』の言葉を拾った短文を気持ちよく書き上げて劇場へ。
『ふたごの星』、『しあわせ日和』、連続稽古。
8月19日
新装なったダンス01スタジオで、10月の「鴎座」上演活動の顔合わせ。
『森の直前の夜』翻訳の佐伯隆幸をはじめ、猛暑の中、参集してくれたスタッフ、キャストに感謝。
演劇という既成のかたちを整えるよりも、伝えたいという衝動に正直に向き合おうとするとき、こころよく手を貸してくれる仲間たちの存在は、ほんとうにありがたい。
顔合わせのあと、『しあわせ日和』稽古。
とりあえずの選曲がうまくいき、作品づくりの方向性が定まった。
8月18日
昼から中野テルプシコール。
舞台監督の森下さん、演出助手の鈴木さんとともに秋の「鴎座」上演の会場下見。
小屋主秦さんの暖かな応対。
この小屋の誠実な活動は彼女の人柄あってのもの。
帰宅後、明日の顔合わせに備えて制作業務いろいろ。
8月17日
仏具(過去帳)を注文に浅草へ出る。
終わって、このところにわかに活気を取り戻しつつある町(何よりも、人通りのエリアの面的な広がりがめざましい)をぶらぶら歩き。
気になっていた、雷門前の浅草文化観光センター(12年4月オープン、隈研吾建築都市設計事務所)を見学。
平屋の家をたてに積み重ねたデザインが物議を呼んでいたが、間近で見た限りでは、外見も中味もいたって平凡なモダン建築。
帰りに立ち寄った、路地の片隅にあった飲み屋兼業の蕎麦屋が大あたり!
8月16日
夏休みを終え、啓子の運転で帰京。
比較的早めに出たせいか、途中、それほどひどい渋滞にも巻き込まれずにすむ。
家に戻る前、工事の終わった「ダンス01」に立ち寄る。
30年目の改装ということで、啓子も感慨深そう。
壁の色の選定など、手伝った内装デザインもまずまずの仕上がり。
8月15日
終戦記念日。
ネットに終戦詔勅の現代語訳が流布している。
『終戦のエンペラー』への違和感もそうだが、最近見られるこのようなこの類の動向には要注意。
「殺されたくはない」ではなく、「殺したくない」という思いにたいする踏みつけは絶対に許せない。
殺人のリアリティは権力者や将軍たちの託宣にではなく、生身の兵士ひとりひとりの身も凍るような体験の中にある。
8月14日
お盆恒例の花火見物。
午後六時、小さな漁港の浜辺に横たわり、志ん生を聞きながら打ち上げを待つ。
午後八時から四十分間、一気呵成の四千五百発。
規模は決して大きくないが、とにかくいまにも火玉が目の前に飛んできそうな間近での見物がご馳走。
コンピュータ制御による組み合わせ演出も、今年は納得。
8月13日
座・高円寺関連の原稿書き二本。
この年齢になって、とりあえず、自分の思いを素直に託せる場を得ている幸運を思う。
「場」、というか人の集まり。
「集まり」、というか群れ。
「群れ」、というか「部族」。
8月12日
広島、長崎の原爆忌、そして8.15と、長い間、日本人にとって八月という月は、自らに課した未来への誓約への思いをあらたにする特別な意味をもっていた。
おのれの「いま」がよりどころとしてきた、言葉にならない悔恨や、慙愧や、無念の叫びやうめき声がはっきりと聞こえる。
はずだ。
はずだった。
「愛国」という言葉のうす汚さ、不潔さに唾を吐きかけてやる。
8月11日
12月に竹田恵子さんと企画している林光さん作曲によるソングコンサート。
山籠もりに持ってきた資料をあたりながら、曲目選びのためのリストづくり。
全四十数曲は、わざわざ一覧表に並べるほどの量ではなかった。
ただ驚くのは、そのほとんどが現在まで、さまざまな場所でさまざまなかたちでうたい継がれていること。
「詠み人知らず」への夢は、あながちただの夢に終わることなく‥‥?
8月10日
何もしないままに一日が過ぎていく。
ような感じ。
悪くない。
十二時前に眠くなり、床へ。
八時間後のすっきりと目覚め。
8月9日
「鴎座」上演活動のチラシ作成追い込み。
デザイナーの太田裕介さんと、終日、メールのやりとりがつづく。
太田さんとは今回がはじめての協働だが、コミュニケーションは順調で、気に入ったデザインが出来上がった。
いつものことだが、チラシが出来上がると上演イメージが一気に具体的になる。
「もう、後には引けない」という覚悟が定まる‥‥へへ。
8月8日
夏休み。
9日間東京を離れ、恒例の山籠もり。
めずらしく昼間のドライブ(啓子運転)だったが、都内、東名その他、道路はどこも自然渋滞の車列。
いつもの二倍ほどの時間をかけて、目的地到着。
土と木々のあいだを通り抜ける微風の香りが出迎え。
8月7日
『ふたごの星』、夏休み前、最後の通し稽古。
三演目の目標にしていた原テキストの読み込みも大分進んで、なかなかいい感じ。
一見何気なく、しかし大胆な実験的上演という意図も、俳優たちの積極的な協力で少しずつ形になりはじめた。
実際に子どもたちを前にしたとき、けいこ場での集中がどの方向に向かって解き放たれるだろうか。
若いころのモットー「新鮮な失敗を」はさすがに揚言できないが、あえて危ない橋を好む性癖は治りそうもない。
8月6日
出張先のホテル。
朝、八時半、TVから流れる式典の鐘の音にあわせて、一分間の黙祷。
こころが騒めく。
死者たちへの祈りというよりも、死者たちとともにする祈り。
生きなければならない「未来のいのち」に向けて。
8月5日
午前中、日比谷での会合のあと、久留米に出張。
出発前、羽田空港ラウンジのPC用デスクを二時間ほど占領して臨時事務室に。
いつもとは違う環境の下、たまっていた雑務がずんずん片づいていく。
途中、デスク脇の大型モニターに沖縄嘉手納基地での米軍ヘリ墜落ニュース。
ショックと「やりきれなさ」で、一気にペースダウン。
8月4日
『ふたごの星』、夏休み前の粗通し。
ぼく役の滝香織さん(今年から参加)のうれしい窯変。
一気に舞台に血が通う。
けいこ場の面白さ。
演出席から芝居にかかわる者だけに許された、申し訳ないような贅沢な瞬間。
8月3日
今日、明日は、午前中から夜まで同じけいこ場に居つづけ。
『ふたごの星』→『しあわせ日和』(ベケット)→『森の直前の夜』(コルテス)。
それぞれにテイストの異なる劇の時間を楽しみながら過ごす。
探求方法も、たどり着こうとする場のありかも道程もまったく違う。
共通するのは、ともに「未知の領域」であること。
8月2日
秋の「鴎座」上演のための、宣伝写真撮影。
笛田宇一郎、竹屋啓子、田村義明の三出演者が揃う。
撮影は学芸大学出身の写真家、神崎千尋さん。
自分の写真を鋏で切り刻んで再構成するコラージュ作家としても、最近、注目を集めている。
撮影は和気藹々(笛田さんひとり、ちょっと緊張気味?)‥‥仕上がりを楽しみに。
8月1日
刺繡作家の吉元れい花さんから小包が届く。
れい花さんらしい、華麗、繊細な金糸の作品。
れい花さんは、桐朋学園演劇科出身の元日劇ミュージックホールのスターダンサー。
昨年偶然再会して以来、折に触れての親しい行き来がつづいている。
刺繡作家として活躍中ということを知って使えそうなものをもっていってもらったなくなった母の刺繍糸が、愛情深く、美しくよみがえった。
