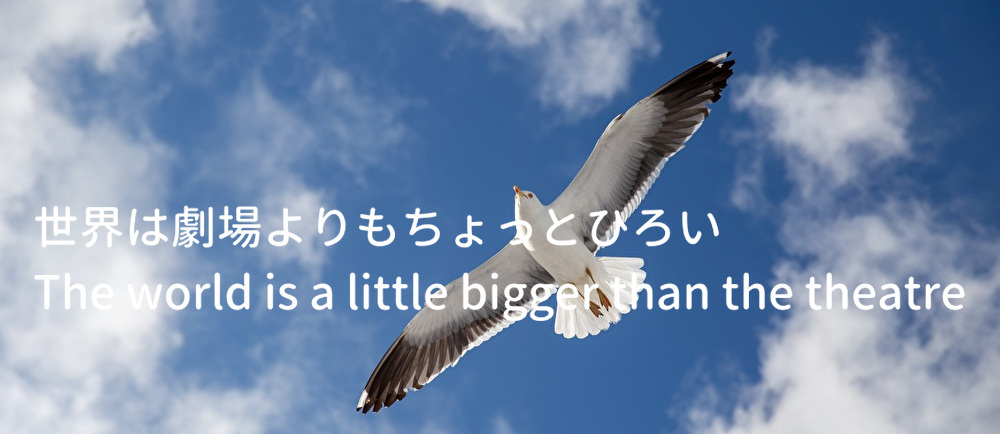
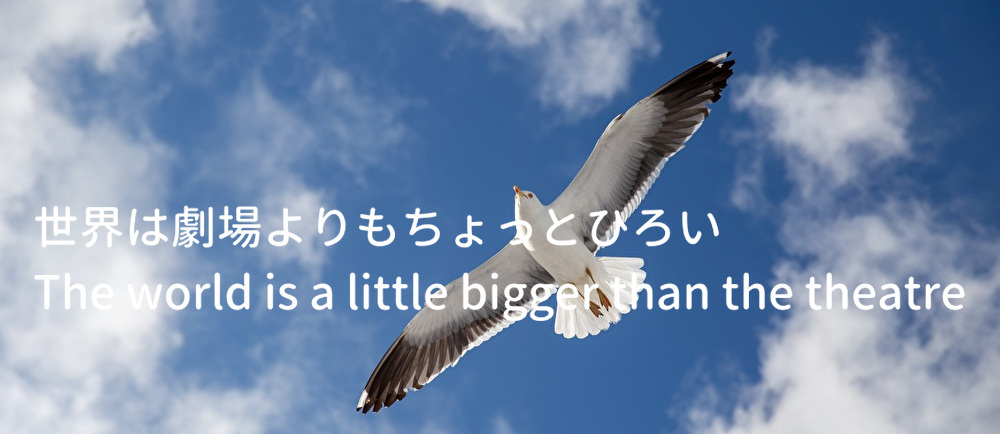
12月31日
朝食後、町で明日の屠蘇用容器を買い物。
昼過ぎ、上演会場の当代芸術博物館へ。
設備のいい(ただし、清掃は問題ありの)小劇場で、一組二時間ずつの場当たりとテクニカルリハーサル。
第一組でリハーサル後、三十分ほどの新聞取材を受けホテルに戻る。
夕方、清水さんを町に連れ出し、ふたりで大晦日の上海の町、ものすごい人出の外湾を、夕食をはさんで五時間、ただひたすら歩き回る。
12月30日
ダニーをのぞく参加者全員で、大型バスで上海へ。
五時間半の長旅を、志ん生、志ん朝を聞いて過ごす。
どこまでも一直線の殺風景な中国高速道路の車窓と落語との不思議なハーモニー。
到着した上海は、会場、宿舎ともに旧万博跡地の近く。
暮れなずむ風景が懐かしい。
12月29日
朝、東南大学でミーティング。
ゲストスピーカーが15人、自己紹介とコメントが一巡したところで、2時間の予定時間。
校内の食堂個室で豪華なランチ宴会。
昆劇院に戻り、クロージング・ミーティング。
夜、若干の手直しをした『駅2013』は今夜も美しい仕上がり。
12月28日
南京公演二日目。
今日から劇場が南京昆劇院、蘭苑劇場にかわる。
マチネ前に、「ワンテーブルトゥチェアーズ」4組とダニーの長編をあわただしく場当たり。
劇場のサイズがコンパクトになったせいもあって、『駅』の上演も納得のいくものに。
シンプルな構成をダニーがほめてくれた。
12月27日
東南大学ワークショップ、二日目。
昨日とは参加者が大部分入れ代わりだったが、急遽つくりなおした新しいシラバスに同行の清水寛二さんにも加わっていただき、今日は納得のいく内容に。
市内の江南劇場に戻り、ランスルー、初日。
上演六作品のうち、今日のベストは、南京虐殺に正面から挑んだ松島誠さんの『記事本』。
アーティストらしい果敢な姿勢に拍手。
12月26日
早起きして、郊外の東南大学へ一時間ほどのドライブ。
今日から二日間、同大学の芸術学院院長が汪さんの招きで、同学院の学生に向けた二日間ワークショップ。
好奇心満々の受講者が三十数人。
通訳を介してのファシリテートに対してちょっと人数が多く、アイスブレークのゲームはともかく、肝心の中味にちょっと集中が欠けてしまった。
反省しつつ、明日に向けてシラバスのつくりなおし。
12月25日
一年ぶりの南京昆劇院。
今年も美しく咲いた庭の蝋梅が出迎え。
劇場で三時間、清水さんと昆劇院の女優徐思佳さんとの稽古。
昆劇女優としての徐さんの力量、柔軟性、創造性にあらためて感嘆。
作品の仕上がりに確信をもつ。
12月24日
今日から南京。
あいにく直行便が飛んでいない曜日なので、上海でのトランジット三時間をふくめて、一日がかりの行程。
制作の延江アキコさんの手慣れたアテンドがこころづよい。
途中、同行の清水寛二(銕仙会)さんと昨日の演能についていろいろ。
それにしても、出会ってから三年目、清水さんの多方面への意欲的な活動には目を見張る。
12月23日
渋谷、観世能楽堂。
銕仙会の重鎮、鵜沢雅さんの追善能。
お嬢さんで、代表的な女流能楽師久さんの『鸚鵡小町』、お孫さんで同じく女流の光さんの『道成寺』披き。
そのほか銕之亟さんの舞囃子など、長時間にわたる多彩な番組。
女性が演じる能の可能性について、さまざまに思いを巡らす。
12月22日
汪暉(訳、石井 剛+羽根 次郎)『世界史の中の中国-文革・琉球・チベット』(青土社)。
三カ月かけて、ようやく読了。
周辺資料を参照しながらの長期読書。
丸山哲史『思想課題としての現代中国』(平凡社)からの流れだが、なんというか現在の自分にとってはさまざまな意味で手応えのある「希望の書」。
知力の衰えに鞭打って、同じ著者の『思想空間としての現代中国』(岩波書店)、その他、孫歌『歴史の交差点に立って』『竹内好という問い』、陳光興『脱帝国』など。
12月21日
ピアノと物語『ジョルジュ』(作、斎藤憐)初日。
昼間、舞台稽古、夜、上演の日程を淡々と。
プレ事業から六年連続上演のレパートリー。
スタッフ、キャスト、観客席ともとどもにかもしだすいかにも劇場らしい独特な雰囲気がとてもいい。
終わって、楽屋でささやかな初日乾杯。
12月20日
啓子の前倒し誕生日。
たっての希望でスカイツリーの予約をとっておいたが、悪天候で断念。
新宿で買い物(含、ささやかなプレゼント)と食事。
夜の時間があいたので、ふたりでアカデミー修了生たちが上演している『アフター・ショック』を観劇に。
早稲田にある小さなギャラリーでの観客十数人の公演だったが、作・演出の樋口ミユ健闘。
12月19日
終日、劇場。
アカデミー修了上演稽古、その他。
風邪ひきの高熱以来、毎日、脳細胞が一定量、ぷちんぷちんと壊れていくような妙な感覚につきまとわれている。
体調は決して悪くない。
仕事もまずまずきちんと片づけているが……はて?
12月18日
昼、帰京。
東京、寒い!
荻窪の100円ショップで、年末の南京行きの小物いろいろ。
食料品のカクヤス、薬局をまわり旅支度の追加。
帰宅後、久留米行き前につくっておいたデータで年賀状印刷。
12月17日
九州、寒い!
終日、会議、ミーティングいろいろ。
昼飯、坦々麺。
晩飯、餃子、釜揚げしらすご飯、その他、たくさん。
仕上げはいつも通り、ジャズ喫茶「モダン」でクリーム入り珈琲。
12月16日
自宅、座・高円寺で雑務少々。
夜、今年最後の久留米行き。
風邪ひきまぎれの休養のおかげで、心身さわやか。
夜、ホテルでのんびりNFL観戦。
ダラスカウボーイズVSグリーンベイパッカーズ。
12月15日
休養日。
新宿に出て、年末の南京行きにそなえて防寒具の買い物。
‥‥のつもりが、衣類や靴など目移りいろいろで思わぬ散財。
秋からの過密日程をなんとか乗り切った自分への贈り物と無理やり納得することに。
夜、啓子と落ち合い新宿で夕食。
12月14日
朝、帰京後そのままの足で明治学院へ。
独文学者谷川道子さん、演出家の岡本章さんが主催した、ドイツの批評家ハンス・レーマンを囲むシンポジウム。
彼が提唱した「ポスト・ドラマ」演劇をキータームに、日本の現代演劇を振り返る果敢なこころみ。
レーマンさんのレクチャーの内容は充実し興味深く、シンポジウム企画も「その意気やよし!」ではあるのだが。
日本側の発表がなべて単調(自分を含めて)で、議論深まらず。
12月13日
大阪。
第二十回OMS戯曲賞審査会。
今年は候補作のレベルが高く、途中三十分ほどの休憩をはさんで、五時間の議論。
終了後、二十回を記念して初回からの審査員渡辺えりさんとともに、これまでの受賞者全員が寄せ書きした色紙をもらう。
OMS以前のキャビン戯曲賞から数えるとかれこれ三十年か。
12月12日
活動再開。
朝、劇場へ出て、美術プランナーの島次郎さん、共同演出の生田萬さん、その他と修了上演の美術打ち合わせ。
舞台美術と衣裳の基本プランをまとめる。
午後は修了上演「戦争三部作」第二部の稽古、Ⅴ期生木野花クラスの発表会GMの稽古など。
明日はギアをもうひとつあげて、大阪へ。
12月11日
熱、引かず。
午前中、啓子の車で近所の医者へ。
幸いインフルエンザは免れたが、今日一日は安静の通告。
処方された薬を飲み、昼、午後と眠る。
夜、ようやく平熱。
12月10日
昨夜から風邪模様。
朝、四十度近い高熱にベットに横たわったまま各所に電話。
一日のスケジュールをすべてキャンセルして、ひたすら眠る。
食欲、まったくなし。
熱にうかされながら見る夢は、色鮮やかなフルカラー。
12月9日
今年八月に改装したダンス01のスタジオ拓き。
自分でも内装デザインに少し口を出して出来上がった明るいスタジオがうれしい。
来年からは、「青劇場」という名のスタジオパフォーマンス会場としても利用するらしい。
祝いの舞は、啓子の日舞「松の緑」と、メンバー大西いずみさんのフラメンコ。
50人近い人びとが集まり、和気藹々。
12月8日
「林光〈うた〉のカバレット」、二日目(マチネ)。
客席で竹田恵子さんの歌を聞きながら、かつての日々が胸によみがえる。
光さんと夢中になって共同作業した時期は四つ。
自由劇場の立ち上げから『鼠小僧次郎吉』連作の前まで、黒テント初期の昭和三部作、「赤い教室」、『赤電車』『鼠たちの伝説』『白いけものの伝説』三部作。
なんと恵まれた時をそれと知らずに過ごしていたのだろう。
12月7日
「林光〈うた〉のカバレット」。
昼、明かりあわせをかねた舞台稽古のあと、7時からソワレ公演。
ピアニストの高橋悠治さん、田川律さんなど、懐かしい顔いろいろ。
60年代後半からの光さんとの共同作業が、一周まわって(本日、参議院を通過、成立)こんな形でよみがえるとは。
夜、国会前で大勢の抗議する若い人びとの姿を見、声を聞く。
12月6日
アカデミー修了上演の稽古はじまる。
四回目の『戦争三部作』。
ようやく三部一挙上演まで辿り着いた。
第二部の本読み、のびのびと始まる。
このまま、見晴らしのいい稽古場を、是非!
12月5日
若い制作者の集まりで講演とシンポジウム。
三つの劇場(スパイラルホール、世田谷パブリックシアター、座・高円寺)での遍歴を通して、劇場のプログラミングについてを報告。
F/T実行委員長の市村作知雄、ウィーン芸術週間の演劇部門ディレクターのシュテファニー・カープ、ドラマトゥルクのマティアス・ピース(ドイツ)と語り合う。
……はずであったが、焦点定まらず不完全燃焼。
残念。
12月3日
昨日の探し物、案の定、今日は劇場到着後三分で発見。
デスクの脇机にきちんと置かれてあった。
なんだろう、六十五歳を越えるころから、「紛失」よりも頻繁に起こる「出現」現象に悩まされる。
しかし、なにはともあれ一件落着。
夜は、水道橋シビックホールで「林光〈うた〉のカバレット」稽古。
12月2日
アカデミーで講師をお願いしている木戸敏郎さんと座・高円寺で、来年夏の企画についての二回目の打ち合わせ。
なくなった作曲家の柴田南雄以来、久しぶりの現代音楽への取り組みが楽しみ。
終わって、次の打ち合わせまでに再度目を通しておこうと以前頂いた資料を探すが、デスク周辺のどこにも見当たらない。
最近は、毎日、二、三度かならず経験する珍しくない現象。
対処方法は、あわてず騒がず、時間と日を置いて次の機会に。
12月1日
母の三回忌を愛宕山の菩提寺で。
一周忌を小祥忌、三回忌を大祥忌と呼ぶそうだ。
法要後の法話で知る。
参会してくれた親戚に、先日まとめた母の歌集「花ひそやかに」を贈る。
父、弟、敦ともども、母もまた、これで自分のなかにだけ生きる存在となっ
